やまなし
宮沢賢治
小さな谷川の底を写した、二枚の青い幻灯です。
一、五月
二ひきのかにの子供らが、青白い水の底で話していました。
「クラムボンは笑ったよ。」
「クラムボンはかぷかぷ笑ったよ。」
「クラムボンははねて笑ったよ。」
「クラムボンはかぷかぷ笑ったよ。」
上の方や横の方は、青く暗く鋼のように見えます。
そのなめらかな天井を、つぶつぶ暗いあわが流れていきます。
「クラムボンは笑っていたよ。」
「クラムボンはかぷかぷ笑ったよ。」
「それなら、なぜクラムボンは笑ったの。」
「知らない。」
つぶつぶあわが流れていきます。
かにの子供らも、ぽつぽつぽつと、続けて五、六つぶあわをはきました。
それは、ゆれながら水銀のように光って、ななめに上の方へ上っていきました。
つうと銀の色の腹をひるがえして、一ぴきの魚が頭の上を過ぎていきました。
「クラムボンは死んだよ。」
「クラムボンは殺されたよ。」
「クラムボンは死んでしまったよ・・・・・・。」
「殺されたよ。」
「それなら、なぜ殺された。」
兄さんのかには、その右側の四本の足の中の二本を、
弟の平べったい頭にのせながら言いました。
「分からない。」
魚がまたつうともどって、下の方へ行きました。
「クラムボンは笑ったよ。」
「笑った。」
にわかにぱっと明るくなり、
日光の黄金は、夢のように水の中に降ってきました。
波から来る光のあみが、
底の白い岩の上で、美しくゆらゆらのびたり縮んだりしました。
あわや小さなごみからは、
まっすぐなかげの棒が、ななめに水の中に並んで立ちました。
魚が、今度はそこらじゅうの黄金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、
おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また上の方へ上りました。
「お魚は、なぜああ行ったり来たりするの。」
弟のかにが、まぶしそうに目を動かしながらたずねました。
「何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。」
「取ってるの。」
「うん。」
そのお魚が、また上からもどってきました。
今度はゆっくり落ち着いて、ひれも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、
お口を輪のように円くしてやってきました。
そのかげは、黒く静かに底の光のあみの上をすべりました。
「お魚は・・・・・・。」
そのときです。にわかに天井に白いあわが立って、
青光りのまるでぎらぎらする鉄砲だまのようなものが、いきなり飛びこんできました。
兄さんのかには、はっきりとその青いものの先が、
コンパスのように黒くとがっているのも見ました。
と思ううちに、魚の白い腹がぎらっと光って一ぺんひるがえり、
上の方へ上ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、
光の黄金のあみはゆらゆらゆれ、あわはつぶつぶ流れました。
二ひきはまるで声も出ず、居すくまってしまいました。
お父さんのかにが出てきました。
「どうしたい。ぶるぶるふるえているじゃないか。」
「お父さん、今、おかしなものが来たよ。」
「どんなもんだ。」
「青くてね、光るんだよ。はじが、こんなに黒くとがってるの。
それが来たら、お魚が上へ上っていったよ。」
「そいつの目が赤かったかい。」
「分からない。」
「ふうん。しかし、そいつは鳥だよ。かわせみというんだ。
だいじょうぶだ、安心しろ。おれたちはかまわないんだから。」
「お父さん、お魚はどこへ行ったの。」
「魚かい。魚はこわい所へ行った。」
「こわいよ、お父さん。」
「いい、いい、だいじょうぶだ。心配するな。
そら、かばの花が流れてきた。ごらん、きれいだろう。」
あわといっしょに、白いかばの花びらが、天井をたくさんすべってきました。
「こわいよ、お父さん。」
弟のかにも言いました。
光のあみはゆらゆら、のびたり縮んだり、
花びらのかげは静かに砂をすべりました。
二、十二月
かにの子供らはもうよほど大きくなり、
底の景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。
白いやわらかな丸石も転がってき、
小さなきりの形の水晶のつぶや金雲母のかけらも、流れてきて止まりました。
その冷たい水の底まで、ラムネのびんの月光がいっぱいにすき通り、
天井では、波が青白い火を燃やしたり消したりしているよう。
辺りはしんとして、ただ、いかにも遠くからというように、
その波の音がひびいてくるだけです。
かにの子供らは、あんまり月が明るく水がきれいなので、
ねむらないで外に出て、しばらくだまってあわをはいて天井の方を見ていました。
「やっぱり、ぼくのあわは大きいね。」
「兄さん、わざと大きくはいてるんだい。
ぼくだって、わざとならもっと大きくはけるよ。」
「はいてごらん。おや、たったそれきりだろう。
いいかい、兄さんがはくから見ておいで。そら、ね、大きいだろう。」
「大きかないや、おんなじだい。」
「近くだから、自分のが大きく見えるんだよ。
そんならいっしょにはいてみよう。いいかい、そら。」
「やっぱりぼくのほう、大きいよ。」
「本当かい。じゃ、も一つはくよ。」
「だめだい、そんなにのび上がっては。」
また、お父さんのかにが出てきました。
「もうねろねろ。おそいぞ。あしたイサドへ連れていかんぞ。」
「お父さん、ぼくたちのあわ、どっち大きいの。」
「それは兄さんのほうだろう。」
「そうじゃないよ。ぼくのほう、大きいんだよ。」
弟のかには泣きそうになりました。
そのとき、トブン。
黒い丸い大きなものが、天井から落ちてずうっとしずんで、
また上へ上っていきました。きらきらっと黄金のぶちが光りました。
「かわせみだ。」
子供らのかには、首をすくめて言いました。
お父さんのかには、遠眼鏡のような両方の目をあらん限りのばして、
よくよく見てから言いました。
「そうじゃない。あれはやまなしだ。流れていくぞ。
ついていってみよう。ああ、いいにおいだな。」
なるほど、そこらの月明かりの水の中は、やまなしのいいにおいでいっぱいでした。
三びきは、ぼかぼか流れていくやまなしの後を追いました。
その横歩きと、底の黒い三つのかげ法師が、合わせて六つ、
おどるようにして、やまなしの円いかげを追いました。
間もなく、水はサラサラ鳴り、天井の波はいよいよ青いほのおを上げ、
やまなしは横になって木の枝に引っかかって止まり、
その上には、月光のにじがもかもか集まりました。
「どうだ、やっぱりやまなしだよ。よく熟している。いいにおいだろう。」
「おいしそうだね、お父さん。」
「待て待て。もう二日ばかり待つとね、こいつは下へしずんでくる。
それから、ひとりでにおいしいお酒ができるから。
さあ、もう帰ってねよう。おいで。」
親子のかには三びき、自分らの穴に帰っていきます。
波は、いよいよ青白いほのおをゆらゆらと上げました。
それはまた、金剛石の粉をはいているようでした。
私の幻灯は、これでおしまいであります。
※作品「やまなし」の掲載について
宮沢賢治が亡くなったのは今(2011年)から78年前の1933年。
著作権法では、個人作品の著作権は没後50年で消滅する事、
また、私自身、光の描写、心の葛藤、読む度に様々な物事を
投げかけてくれるこの素晴らしい作品を読み、そして感じる事があり、
ご訪問いただいている方にもご紹介したいと思った事から、
原文のまま掲載させていただきました。
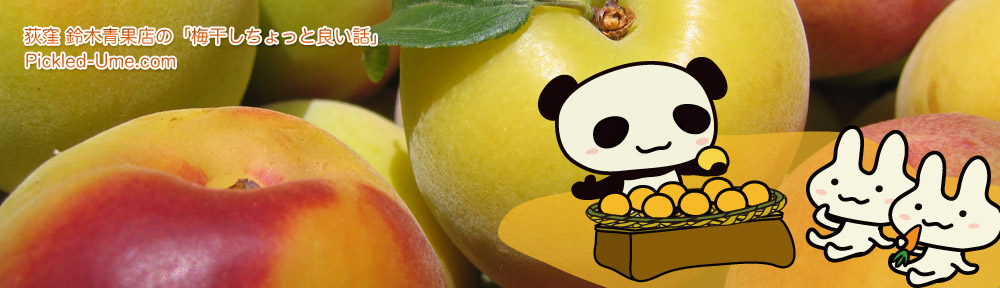



 SShin1
SShin1

